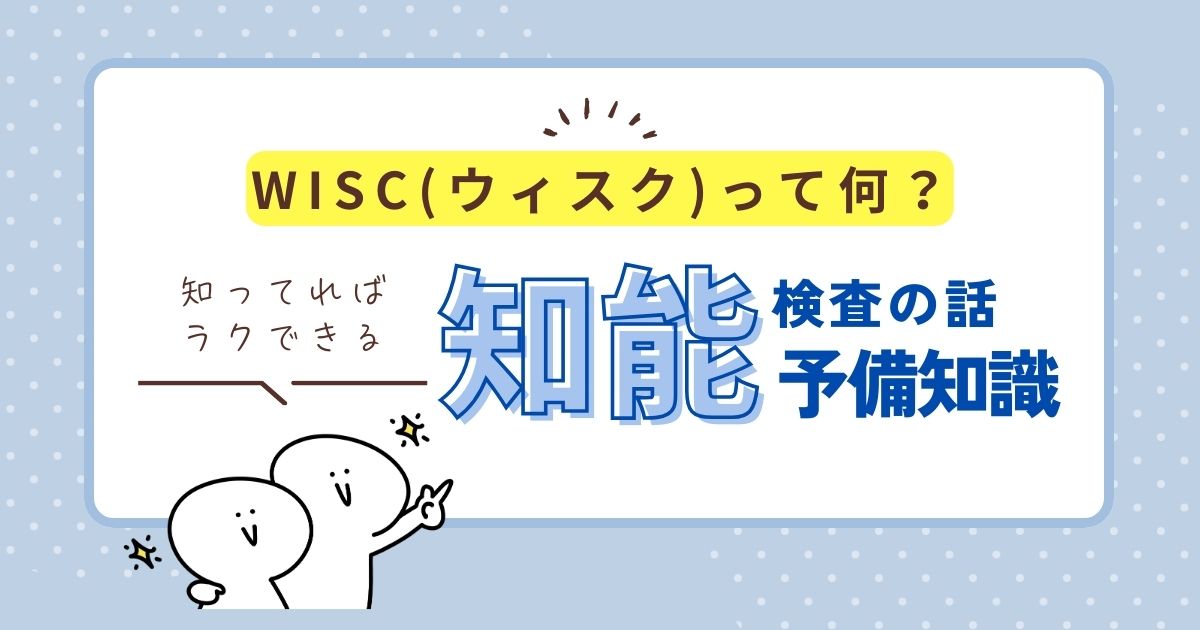こんにちは、公認心理師&特別支援教育士のあべ子です^^
特別支援学級の在籍でなくても、個別の教育支援計画や個別の指導計画を立てているというお子さんはたくさんいると思います。
個別の教育支援計は、知能指数(IQ)について、検査結果がよく付記されていると思いますが、
・IQだけ確認して終わり。
・専門用語がたくさんあってどれがどれか分からない。
・この結果と児童の実態がどう結びつくのかピンとこない。
・指導への反映のさせ方がわからない。
といった理由から、書類を受け取った時以外は滅多に見ることもない、という先生方も中にはいらっしゃるのではないかと思います。
私は前職で、知能検査を実施し、その結果からお子さんへの指導や支援の方法を考え、保護者や学校の先生にお伝えするというお仕事をしていました。
結論から言うと、知能検査の結果には、先生方がそのお子さんとの関わりやすさを格段にアップさせるためのとても有益な情報がたくさん含まれているので、
参考にしないともったいない!
というのを声を大にして言うべく、知能検査に関する記事を書くことにしました。
知能検査は、主に児童相談所、教育センター、病院などで受けることができます。
その結果をまとめた「検査所見」や「検査結果報告書」なる書類を保護者の方から学校に提出され、個別の教育支援計画に資料として添付されているケースが多いかと思いますが、
そこで、学校の先生が目にする機会が多いと思われるWISC(ウィスク)と呼ばれる知能検査について、知っておくと教育現場での実践に役立つポイントがいくつかありますので、これから書いていきたいと思います。
知っておくとこの先ずーっと使える知識だと思うので、ぜひ読んでみて下さい。
そもそもなぜ知能検査をするの?

知能検査とは、知能を測る検査。
その人の知的な能力について詳細に調べる検査です。
知能検査は、学習や学校生活上で何らかの困り事が生じていたり、生きづらさを感じたりしている子どもたちが何かしらのサポートを受ける際に、その子の状況を理解してより良いサポート案を考えるための情報を得るために行います。
例えば「漢字が覚えられない」という表面上の困り事は同じでも、その原因はお子さんによって様々です。知能検査の結果に基づいて、対応の仕方や指導の手立てもその子に合ったものにすることができるのです。
また、ご本人の自己理解や、保護者さんに理解を促すことも、大切なねらいです。
人間が持つ能力は、知的な能力だけではありませんが、子どもたちが抱える困り事の多くは知的な能力が関わっていることが多いため、知能検査は、必ずと言っていいほど、どこの病院や相談機関でも実施されます。

知能検査は、知的障害の目安にはなりますが、ASDやADHDかどうかを判断することはできません。
WISCって何?

現在、日本でよく使われる知能検査は数種類あり、WISCはその中でもシェア率が高いものの1つです。

車に例えるとトヨタみたいな感じかな。
で、このWISC(ウィスク)というのは、
Wechsler Intelligence Scale for Children
の頭文字となっております。
Wechsler:ウェクスラーさんという人が考案した
Intelligence:知能
Scale:測定するもの
Children:子ども用
子ども用ということは、大人用も他にあるんですよ。
あと、幼児さん向けも。
ここでは触れませんけど。
もとはアメリカの検査なんですが、これを日本人の文化的な背景やらなんやらを加味して、「日本版」というのを作って使っています。

日本中あちこちで、いろんな子がWISCを受けています。
また、あとの時代に生まれた人のほうが昔の人よりも知能が高い傾向があるという説があり(フリン効果)、WISCは約10数年ごとに改訂され、問題の中身や検査の構成なども、その時代に合った内容や最新の研究結果が反映されるようになっています。
日本版WISCは、2021年に発行された「第5版」が一番新しいもので、表記としては「WISC-Ⅴ」となります。
ただし、最新版が出たからと言って機械的にすべて一律で切り替わるわけではなく、検査道具の導入(検査用紙やマニュアル等で20万円ぐらい必要!)や検査者の研修などの都合があるので、しばらくの間は以前の物(WISC-Ⅳ)を使う所も多くあり、それはそれで特に問題はありません。
なので、先生方が目にする書類には、WISC-ⅣまたはWISC-Ⅴの結果が書かれていることが多いかと思います。
また小1の子は、入学前に幼児さん向けのWPPSI(ウィプシ)を受けている子もいるかも知れません。
WISC知能検査は、世界的にスタンダードな子ども用の知能検査で、児童生徒の実態把握や支援方法の検討のために欠かせない検査です。
どんなことをするの?


腹筋何回できるとか?

残念ながら、運動能力は測りません。あと、芸術系の才能とかもわかりません。そういった意味でも、知能検査からは人間のほんの一部分しか知ることができない、という点は念頭に置いておくべきです。
WISCは、相談室などの静かな部屋で、検査者(心理職などの検査を行う大人)とお子さんの1対1で着席して行います。
通常は、小さなお子さんでも保護者の方と離れて、検査を受けてもらいます。
検査の内容は、検査者の質問に対して口頭で答えてもらったり、絵を指さしして答えてもらったり、指示の通りに道具を操作してもらったりするような課題を次々とこなしてもらいます。
所用時間は、検査自体は60~90分くらい、前後の時間も含めると2時間くらいです。
入学前や低学年のお子さんであれば、保護者と離れて、着席し続け、不慣れな環境下でも検査を受けられるか、そして少なくともその検査が成立するような回答ができるかどうかによって、学習レディネスが育っているかを知る手がかりになるので、報告書に書かれている「検査中の様子」もよく読んでみてください。
まとめ
今回は導入編として、知能検査の基本知識について解説しました。
知能検査で発達障害かどうかを直接知ることはできませんが、「どうして困り事が生じているのか」ということの背景や、本人に合った指導方法を知る重要な手がかりになります。
次回は、検査結果でまず見て欲しい数値とその意味について解説します。ぜひ参考にしてみてください。