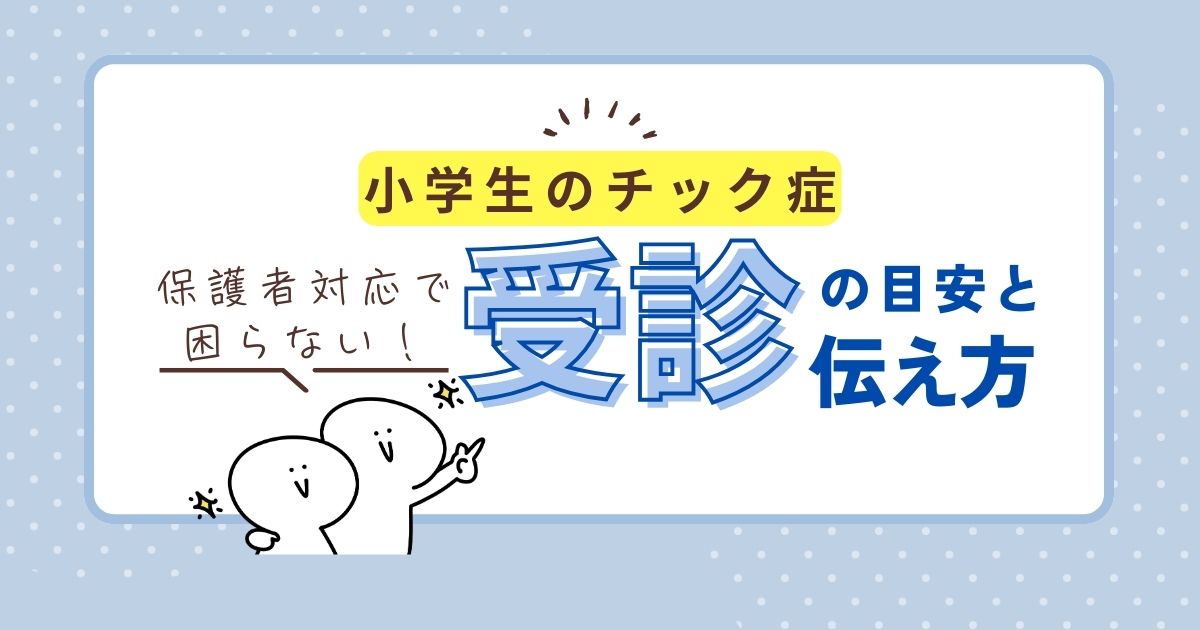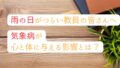こんにちは、公認心理師&特別支援教育士のあべ子です^^
チック症はさほど珍しい症状ではなく、多くの先生が今までにチック症の児童を受け持った経験があるようです。
チック症は1年程度で自然と軽減していく(そのため、周囲はあまり過剰に反応せず見守るようにするのが望ましい)と言われていますが、そうでないお子さんも中にはいます。
学校生活上のサポートが必要と思われたり、心配した保護者の方から相談されたという先生もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、今回はチック症の医療受診の目安についてまとめました。また、学校から保護者の方に病院のことを勧めたほうがいいのかについても考えていきます。
チックについての基本知識については、こちらをご覧ください。

チック症状自体は、あってはいけないものや無くすべきものではありません。
しかしチック症状が長引いていたり学校生活に支障があったりすると、学校としても「見守りだけで本当にいいのか」と不安になるでしょうし、専門的な助言を踏まえたうえで対応したいと思うのが先生方の本音だと思います。
一番は本人の健やかな成長のためですから、この記事の内容を参考にしつつ、保護者の方と足並みをそろえて対応していきたいというスタンスでお話をされてみてはいかがでしょうか。
病院を受診する目的

まず、病院を受診するということは、”病気かどうか診断をしてもらって、医学的な治療を受ける(その必要性を判断してもらう)”ということです。
”チックの治療”には、薬物療法、心理療法、親子関係の調整、チックの背景にある疾病への対応などがあり、お子さんの状態に応じてこれらを効果的に組み合わせて治療が行われます。
単に“チック症状がある”というだけでは、“治療が必要”というわけではないため、チック症状がある人が全員受診する必要があるというものではありません。
その症状によって生活に影響が出ている場合や、その他の困りごとがあるといった場合に、それを解決するための方法の1つという風に考えましょう。
受診の目安
症状が長期化している
チックは一時的なもので、自然に軽減していくことが多いですが、1年以上症状が続く場合は受診を検討しましょう。
長びくチックは、持続性チック症やトゥレット症候群の可能性があります。
このような場合は、本人が自信を無くしていたり、学校生活でも何らかのサポートが必要なことが出てきたりしていることが少なくなく、診断を受けることで適切な治療や支援につながることから、保護者との間で病院のことを話題にすることは、むしろ自然なことだと思います。
症状が重度で日常生活に支障がある
チックが日常生活や学校生活に影響を及ぼす場合は受診しましょう。
例えば、手が動くチックでノートテイクが進まない、体が動いて食べ物をこぼす、学校に行きたがらないなどの症状がある場合です。
これらは子どもの学習や社会性の発達にも関わってくるので、やはり医師の助言を仰ぎたいところです。
本人が症状を気にしている場合
お子さん本人がチックを気にして悩んでいる場合は、受診を考えてもよいと思います。
自尊心の低下や社会的な不安につながる心配があるため、本人の気持ちを大事にしつつ、一緒に前向きに取り組んでいく姿勢が大切です。
適切な対処法を学ぶことで本人が安心できるというメリットもあります。
他の症状を併発している
チック症は、他の発達障害や精神疾患が合併することがあります。
注意欠如・多動症(ADHD)、自閉スペクトラム症(ASD)、学習障害などの症状が見られる場合は、総合的に見て対応を考えていく必要があります。
これらの合併症があるかないかによって治療方針が異なってくることもあり、専門医による適切な診断が重要になると思われます。
保護者の不安が強い
保護者が子どものチックに強い不安を感じている場合も、受診を検討する理由になります。
仕方がない面もありますが、保護者が自分でネットで調べて余計に不安になったり、あやふやな情報に振り回されたりすることがどうしてもあります。
また、チックには遺伝的な要因があるとも言われており、保護者自身がもともと不安になりやすい面を持つケースも中にはあるでしょう。
保護者の不安が子どもに伝わることは、あまり良い影響があるとは言えませんから、そういった意味で、医師から直接お話を聞くことで保護者の不安が軽くなったり適切な対応方法を知ったりすることができるのは、本人にとってメリットがあると言えるでしょう。
保護者に受診を勧めることは問題ない

学校が保護者に病院の受診を勧めることは、基本的には問題ありません。
ただし誤解を受けたり思わぬトラブルに発展したりする恐れもゼロではありませんから、次のような点に気を付けると良いと思います。
- お子さんの状態を客観的に観察し、具体的な症状や影響を保護者に伝える。
- チック症は意志の力で止められないものであることを理解し、お子さんを責めたり否定的な反応をしないよう注意する。
- 保護者との信頼関係を築き、児童の最善の利益を考えて話し合う。
- 学校での支援体制を整えるために、専門家の助言を得ることの重要性を伝える。
- 受診後も、学校と家庭が連携して児童をサポートする体制を整える。
保護者の気持ち
保護者が担任の先生から子どものチック症状について病院受診を勧められた場合の感情や反応には、さまざまなものが予想されます。
ポジティブな反応
- 信頼感や感謝の気持ち
先生が子どものことを真剣に考え、適切な助言をしてくれたと感じるでしょう。特に、説明が丁寧で具体的であれば、先生への信頼が深まる可能性があります。 - 安心感
子どもの症状に気づいてくれる人がいることで、保護者が孤立感から解放される場合もあります。専門機関の受診を勧められることで、解決策が見つかる期待を抱くケースもあると思われます。
ネガティブな反応
- 不快感や不安
先生からの指摘が過干渉だと感じたり、自分の育児を否定されたように受け取る保護者もいるかも知れません。また、「病院」という言葉自体に抵抗感を持つ場合もあります。 - トラブルの可能性
提案の仕方が一方的だったり、病院を指定して受診を急かすといった具体的すぎるアプローチは、保護者との間で摩擦を生むことがあります。特に、受診に対して慎重な反応を示している場合は、過去に医療機関で嫌な経験があったり、家族間で意見の相違を抱えて葛藤している可能性があるため、無理強いは禁物です。

病院の話を出す時は、トラブル防止のため、特支コーディネーターや管理職と事前に情報共有するという決まりを作っている学校もあるよ。
受診を勧める際の伝え方

保護者に受診について話す場合は、保護者が安心して検討できるよう配慮しつつ、信頼関係を築くことを念頭に置きましょう。保護者とのトラブルを避けつつ信頼を得られるような伝え方にはいくつかのポイントがあります。
丁寧な説明
子どもの症状や学校での様子について具体的に説明し、医療機関受診の必要性を冷静かつ客観的に伝える。
(例)
「お子さんの最近の様子についてお話させていただけますか。授業中や休み時間に、まばたきや肩をすくめる動作が頻繁に見られることがあります。これらは意図的ではないようで、お子さん自身も困っている様子です。こうした症状は、チック症状の可能性が考えられます。専門家に診てもらうことで、原因や適切な対処法が分かるかもしれませんが、今まで、どこかに相談されたりしたことはありませんか?」
共感的な姿勢
保護者の不安や葛藤に寄り添いながら話すことで、安心感を与える。
(例)
「お子さんのことで心配されているお気持ち、とてもよく分かります。私も学校での様子を見ていて、お子さんがストレスを感じているのではないかと気になっています。一緒に考えていければと思いますので、ぜひご相談ください。」
選択肢の提示
医療機関受診はあくまで一つの選択肢であると伝え、押し付けない。
(例)
「医療機関への受診についてですが、無理に急ぐ必要はありません。ただ、チック症状が続く場合には、小児科や児童精神科で相談することも一つの方法です。もし迷われるようでしたら、まずは地域の教育相談センターやスクールカウンセラーにご相談いただくこともできます。学校での様子は引き続き注意深く見ていきますから、ご家庭でも一度考えてみて下さい。」
まとめ
病院を受診するかどうかは、本人の気持ちや保護者の方の考えに基づくことが大前提ではありますが、この記事にあるような状況に当てはまる場合は、本人がつらい思いをしている可能性もあるので、学校から保護者の方へ医療機関に相談したことがあるのか一度聞いてみてもいいかも知れませんね。
ただし、保護者の方が受診に対して慎重な姿勢を見せる場合は、それを尊重することも時には必要です。

受診がお子さんのためであることは疑いようのない事実ではありますが、正論であればあるほど、相手は心理的な逃げ場がなくなって”守り”の姿勢に入ってしまいますから、こちらは柔軟な姿勢でいるほうが無難です。