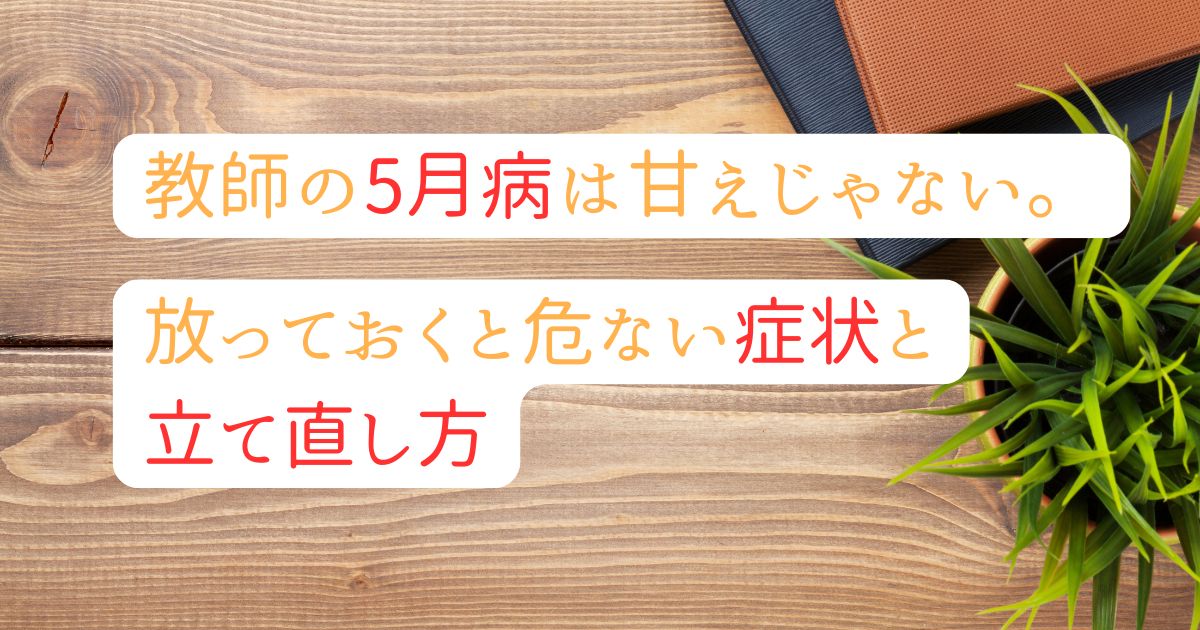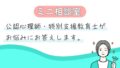新年度のバタバタもひと段落する5月。
ふとした瞬間に、こんなふうに感じていませんか?
「何をしても疲れが取れない」
「教室に行く足が重い」
「自分だけがうまくできていない気がする」

それ、もしかすると「5月病」のサインかもしれません。
特に教師という仕事は、4月から急激に責任と期待がのしかかるため、5月に心身のバランスを崩しやすい傾向があります。
初任の先生だけでなく、何年目のベテラン教師でも、知らず知らずのうちに無理を重ねてしまうことは珍しくありません。
この記事では、教師に多いと言われる5月病の症状や原因、休職せずに乗り切るための方法などについてまとめています。
ゴールデンウィーク明け以降、少しでも心や体に違和感を感じているなら、ぜひ最後まで読んでみてください。
無理に頑張り続けなくても大丈夫。
ここから、自分を守るための一歩を一緒に考えていきましょう。
教師に増えている「5月病」とは?
4月、気合いを入れてスタートを切ったはずなのに、5月に入ると急にやる気が出なかったり、疲れが取れなかったり……。
そんな「5月病」、実は教師という職業にとってかなり身近な問題です。
しかも、初任の先生だけでなく、何年目の先生でもかかる可能性があるんです。
ここでは、5月病の基本的な正体と、なぜ教師に多く見られるのかを整理してみます。
5月病の基本的な定義と特徴
5月病とは、新生活や新年度の環境変化に適応しきれず、心や体に不調が現れる状態を指します。
医学的な正式名称ではありませんが、精神科や心療内科でも広く使われている言葉です。
主な症状は次の通りです。
| 心の症状 | 体の症状 |
|---|---|
| ・やる気が出ない | ・倦怠感(だるさ) |
| ・不安感、焦り | ・食欲不振 |
| ・自分を責める思考 | ・睡眠障害(眠れない・寝ても疲れが取れない) |
特に教師は、責任感が強い人が多いので、「もっと頑張らなきゃ」と自分を追い込んでしまう傾向があり、5月病に気づきにくいこともあるそうです。

疲れてるのは”甘えてるだけ”って、自分に鞭を打って奮い立たせてませんか?

界王拳で乗り切ろうと思う。

それ、体がもちません…(ネタは古いが話のつじつまは合うw)
学校現場で起こりやすい理由(教師特有の事情)
教師はなぜ5月病になりやすいのでしょうか?
そこには、学校現場ならではのストレス要因が隠れています。
代表的な理由はこちら。
- 急激な環境変化(新しいクラス・保護者対応・異動など)
- 「子どもたちの前では常に元気で」プレッシャー
- 過度な自己責任感(うまくいかないと自分を責めがち)
- プライベートの時間不足(土日も部活・行事準備)
- 相談しにくい職場風土(悩みを見せるのが「弱い」と思われる?)
特に「4月は全力疾走、5月はガス欠」という現象は学校現場では起きやすいことだと、以前、管理職の先生から聞いたことがあります。
さらに、生徒や保護者の期待に応えようとするあまり、自分の感情を後回しにしてしまう先生も多いんだそうです。

先週「笑顔が固まってますよ」って言われたなー
まとめ: 5月病は誰にでも起こる心と体のSOSサインです。特に学校の先生は、がんばりすぎ&休めなさすぎのダブルパンチで、5月病になりやすい環境にあります。
こんな症状は要注意!教師に現れやすい5月病のサイン
5月病といっても、人によって現れるサインはさまざま。
「なんとなく調子が悪いなぁ」と感じるだけでは見過ごしてしまいがちなので、早めに気づくことが、悪化を防ぐ第一歩です。
ここでは、特に教師に現れやすい心と体のサイン、そして新任・若手教師ならではの兆候についてみていきます。
心の症状(やる気が出ない、不安感、無力感)
まずは心のサインから。
5月病の心の症状は、以下のような形で現れます。
- 仕事へのやる気が出ない(朝、学校に行くのがつらい)
- 不安感が強まる(小さなミスでも「もうダメだ」と思いがち)
- 無力感を感じる(「自分には教師としての資質がない」と思い込む)
- イライラや怒りっぽさ(周囲にあたってしまう)
- 人と関わるのが面倒になる(職員室に行きたくない、会話を避ける)
教師は「子どもたちや保護者の前ではしっかりしなきゃ」という意識が強いぶん、内側で疲労が蓄積しやすいのが特徴です。
また、完璧主義傾向がある先生ほど、「自分はまだまだ頑張れていない」と過剰に自責しがちなので注意が必要です。
▶参考記事
完璧主義で苦しむ人・苦しまない人
https://edu.counselor-haruna.com/perfectionism/
身体の症状(疲れが取れない、頭痛・肩こりなど)
心と体はつながっています。
5月病によるストレスは、身体にも確実に影響を及ぼします。
具体的にはこんな症状が現れやすいです。
- 慢性的な疲労感(十分寝たはずなのにだるい)
- 頭痛や肩こり、腰痛(ストレスによる筋肉の緊張)
- 胃の不調(胃痛、胃もたれ、食欲不振)
- 寝つきが悪い・夜中に目が覚める(睡眠の質の低下)
- 風邪をひきやすくなる(免疫力の低下)
特に学校の先生たちは、「身体の不調=気合いでなんとかする」という謎の根性論がポリシーがあるようで…。
でも、体からのSOSを無視していると、ある日突然「限界」が来てしまうこともあるんですよ。
初任・若手教員に特有のサイン
新任・若手の先生には、さらに特有の5月病サインが見られることがあります。
たとえば──
- 自己肯定感が極端に下がる(「自分だけできてない」と思い込む)
- 人間関係への不安(先輩や同僚とうまくやれているか気になる)
- 初めての壁にぶつかり、急に落ち込む(生徒指導や保護者対応)
- 「辞めたい」と本気で考え始める
学校現場は、良くも悪くも「ベテランの暗黙知」が支配している世界と言われています。
最初からすべて完璧にこなせるわけがないのに、「自分だけできていない」と孤独感を抱えやすいのが、新人・若手の特徴です。

ざわついたクラスをすっと静かにさせるテクとか、「先にそれを教えてよ」みたいなのが多々あるんだよねー。

マニュアル化できないことだらけなんですよね。

1年目の時は、初めての授業参観のあと家で屍になってたよ。
まとめ:教師の5月病サインは、心・体・行動にわたってじわじわ現れます。
「ちょっとおかしいな」と感じたら、がんばりすぎる前に立ち止まる勇気を持ちましょう!
なぜ教師は5月病になりやすいのか?
春から新しいクラス、新しいメンバー、新しい役割。ワクワクする反面、教師という仕事は「理想」と「現実」のギャップに直面しやすい職業です。特に5月は、体力も気力も落ち込みがちなタイミング。なぜ教師は5月病になりやすいのか、主な原因を整理してみましょう。
環境変化(クラス運営、保護者対応、校内人間関係)
4月、教師はまさに環境の変化の嵐の中に放り込まれます。
- 新しいクラス
- 未知の子どもたちとの関係づくり
- 保護者対応(時に厳しい要望も)
- 教員同士の人間関係リセット(学年主任、教科主任、管理職…)
特に最初の1か月は「とにかく頑張ろう!」と目まぐるしく過ぎていきますが、5月になると、
「あれ、なんか思ったより疲れてるな…」
「なんでこんなに気を遣わなきゃいけないんだろう」
という違和感がじわじわ出てきます。
ここで【表】にまとめてみましょう。
| 環境変化の種類 | 教師にかかる負担 |
|---|---|
| クラス運営 | 子どもたち一人ひとりに合わせた対応、学級目標達成へのプレッシャー |
| 保護者対応 | クレームや要望への対応、信頼関係づくりの負担 |
| 校内人間関係 | 上司・同僚・事務方など多方向への配慮 |
まとめ:5月は「新しい環境に適応しようとしてきた負担」が表面化する時期!
過剰な責任感と「理想とのギャップ」
教師はもともと、真面目で責任感が強い人が多い職種です。

わかりみが深いね。うん。

それはよかった💦
特に初任・若手の先生ほど──
- 子どもたちみんなと良い関係を築きたい
- どんな保護者にも信頼されたい
- どんな業務もきちんとこなしたい
という、高い理想像を抱きがちです。
しかし現実には…
- トラブルは起こるし、
- 全員を満足させることはできないし、
- 予定通りに授業が進まないことも当たり前。
この「できない自分」を責めてしまうことが、心のエネルギーを大きく削ってしまいます。
さらに厄介なのが、先ほど触れた「ベテランの暗黙知」。
ベテラン教師たちが、言葉にしなくても自然にできることを、新人の先生は「なんで私だけできないんだろう…」と感じ、さらに自信を失う悪循環に陥るのです。
場合によっては、「なんでやらないの?」ぐらいの厳しい視線を向けられるケースもあります。

知らない&わからないことはできない。やらないんじゃなく、できない。けど、センスの問題とかにされちゃうと、もうヘコむしかないんだよね…。
まとめ:高すぎる理想と現実とのギャップから自己肯定感が下がる。
ストレスがたまりやすい学校特有の風土
学校には、企業や他の職場にはない独特の文化や風土があります。
これがストレスをためやすくする要素にもなっています。
たとえば──
- 常に誰かが見ている(オープンスペース文化)
- 助けを求めづらい(周りがみんな忙しそう)
- 完璧主義が美徳とされる(ミスを許さない雰囲気)
また、最近は少しずつ変わってきているとは言え、休日返上の部活指導や校務分掌による負担も、疲労の蓄積に拍車をかけます。
本来休むべき土日も、心身をリセットするどころか、さらに疲弊してしまいます。
ほかにも、
- 休憩時間が取りにくい
- 個別対応が増え続ける(特別支援、家庭支援など)
- 校内の評価基準があいまい
といった風に、学校特有のストレス要因を書き出してみると、まだまだたくさん出てきます。
まとめ:「条件はみんな一緒。やって当然」という学校特有の空気で精神的に追い込まれてしまう。
休職は避けたい!5月病を乗り越えるセルフケア5選
5月病かなと思っても、「教師失格だ」なんて思う必要はありません。
少し立ち止まって、自分のケアに目を向ければ、ちゃんと回復への道は開けます。
ここでは、教師という忙しい仕事の中でも実践しやすいセルフケアを5つ、ご紹介します。
1. 頑張りすぎない自分にOKを出す
まず一番大事なのが、「頑張れない自分」を責めないこと。
教師という仕事は、「全力で子どもに向き合うのが当然」という空気がありますが、
そもそも常に100点の自分でい続けるなんてムリなんです。
疲れているときに休むのは自然なこと。エネルギーが切れてしまう前に、
「今日はこれができたからOK!」と、自分に小さなマルをあげましょう。
自分に優しくなることは、子どもにも優しくなれる土台になります。

今日、笑顔で『おはよう』が言えたんで、もうそれで100点ってことにします!

それで十分です、ほんとに。
2. 「やらないことリスト」を作る
ToDoリストで毎日が埋まってしまう人こそ、
逆に「やらないことリスト(NOT ToDo)」を作ることをおすすめします。
たとえば──
- 放課後すぐに校務分掌の仕事に取り掛からない
- 昼休みはなるべく1人で過ごす
- 授業準備の仕事を持ち帰らない
- 朝イチでメールチェックしない
- 週に1回は「残業しない日」を作る
といった具合に、「意図的にやらないこと」を決めておくことで、
“脳と心のスペース”が確保され、少しずつ気持ちが楽になります。

“やらない”のは勇気がいりますが、実は“自分を守ること”につながるんです。
3. 校内で1人だけでも「話せる人」を作る
職場に「この人にはちょっとだけ本音を言える」存在がいるかどうかで、
ストレスの蓄積度はまったく変わってきます。
別に愚痴を言う必要はありません。
- 「今日は疲れたね〜」と言い合える
- なんでもない話ができる
そんな“ゆるい味方”を1人見つけておくだけで、
「私は1人じゃない」と感じることができます。
一方で、相性が合わない人との無理な関係構築はストレスになります。
無理にコミュニケーションを広げようとせず、「この人だけいればいいや」と割り切るのも大切な戦略です。
4. オフの日は「学校のことを一切考えない」時間を持つ
意外とやってしまいがちなのが、休みの日の“思考残業”。
- 明日の授業準備どうしよう…
- あの子の対応、間違ってたかも…
- 保護者面談、ちゃんとできるかな…
こういった考えが頭から離れないと、せっかくの休日も回復の時間になりません。
かといって、まったく考えないようにするのは難しいというもの。
おすすめは、「学校のことを考えない時間」を意識的に作ること。
たとえば──
- 午前中はとことん寝る(アラームOFF!)
- 1人でのんびりカフェ
- 好きなYouTubeで爆笑(教育系じゃないやつ)
- 「仕事の話禁止」の友達とランチに行く
こうした時間は、脳のストレス処理にも効果的です。

無になる時間、絶対必要!

家族サービスに集中するのがストレス解消になる人もいれば、逆に、「一人時間がないと無理!」という人もいます。自分のタイプを把握しましょー。
5. 心身のSOSを早めにキャッチして休む
最後に何より大切なのは、自分の「疲れサイン」に早く気づくこと。
- 朝起きても動けない
- 涙が勝手に出る
- 忘れ物やミスが増える
- 子どもに対して感情的になってしまう
- 人と話したくなくなる
これらは、心や体が「限界に近いよ」と教えてくれているサインです。
「でも休んだら迷惑がかかる…」と考えるかもしれませんが、
倒れてから休むより、早めに手当てするほうが、ずっと回復は早くなります。
もし、心療内科やカウンセリングに行くハードルが高いと感じるなら、
まずは保健室の養護教諭、信頼できる先輩教員など、“ちょっと話せる相手”を探すところからでもOKです。

5月病は、「真面目に頑張ってきた人」がかかりやすいものです。
焦らず、責めず、丁寧に、自分のエネルギーを回復させていきましょう。
それでもつらいときは?相談できる場所とサポート先
どんなにセルフケアを頑張っても、「もう限界…」と思う日があるかもしれません。
そんなときに備えて、相談できる場所や使える支援先をあらかじめ知っておくことは、自分を守るための大切な備えです。
ここでは、教師が利用できる具体的な相談窓口や支援についてご紹介します。
校内の相談窓口(養護教諭、スクールカウンセラーなど)
まずは、校内にいる身近な専門職を頼ってみましょう。
- 養護教諭(保健室の先生)
- スクールカウンセラー
- 教頭・管理職(※信頼できる場合)
たとえば、「最近朝がつらい」「気分が落ち込む」など、
言葉にしにくい不調でも、まずは“つぶやくように話す”ことから始めてOKです。
養護教諭は、健康面だけでなく、心のケアにも理解があります。
スクールカウンセラーは原則、児童生徒支援がメインではありますが、教職員からの相談も可能です。

「話す=手放す」と言います。言葉にして話してみたら、それだけでもずいぶんラクになったという人は多いですよ。
教育委員会の相談センター
次に、教育委員会や教職員互助組合が設置する相談窓口も活用できます。
多くの自治体では、以下のような窓口があります。
- 教職員健康相談センター
- 教育相談室(メンタルヘルス専用)
- 産業医や外部カウンセラーとの連携サービス
匿名で相談できる場合や、電話・メールでの対応が可能なところもあります。
また、「病休・休職に入るべきか迷っている」段階での相談も受け付けています。
外部のカウンセリングサービスを利用する
校内や教育委員会の相談以外にも、民間のカウンセリングサービスを利用する方法があります。
以下のような特徴があります:
- オンラインで全国対応しているところが多い
- 匿名で受けられる
- 教育現場に詳しいカウンセラーが対応してくれる場合もある
また、最近はLINEやZoomなどを使った気軽なメンタルヘルス相談も増えてきました。
料金が気になる方は、自治体や互助組合が費用を補助しているカウンセリングもチェックしてみてください。
「相談=負け」ではないという考え方
「でも、相談しても仕事が減るわけじゃないから意味ない…」
「メンタルやられた先生、ってレッテルが張られないか心配」
そんなふうに感じて、一歩踏み出せない人も多いと思います。
でも、相談は“負け”ではありません。
むしろ、それは「自分を維持するための、必要なメンテナンス」です。

周囲の目とか、将来のキャリアとか、色々気になっちゃうんだけど…

一番大事なのは、先生自身の心と体です。
助けてって言っていいし、言わなくちゃいけないんです。
実際、早めに相談したり休職したりすることで短期間で回復できる可能性が高まります。
つらいときは、必ず誰かに頼ってください。
教師という仕事は”1人で抱え込む”には重すぎます。
あなたの味方は、必ずどこかにいます。
「味方なんていないよ!」と思う先生には、私が必ず味方をしますよ!