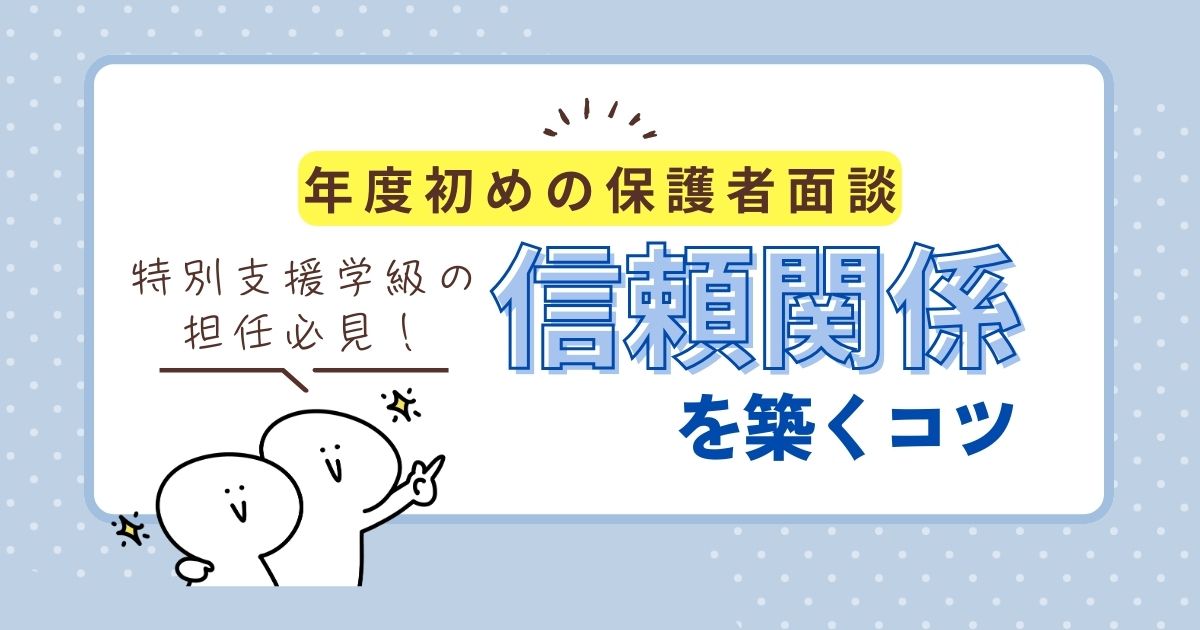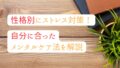なぜ「年度初めの面談」が保護者との関係づくりにおいて重要なのか?
「最初の面談って、なんだか緊張する…。」
「一体何をどこまで話すべきなのか…」
特別支援教育に関わる先生なら、誰もが一度は感じたことがあるのではないでしょうか。
年度当初の保護者面談は、保護者との信頼関係づくりの“スタート地点”です。
この場の印象が、その後の学校との関わり方や、支援への受け止め方に大きく影響します。
特別支援学級の児童生徒の保護者は、時に不安や葛藤を抱えています。
「うちの子は学校で頑張れているかな?」
「学校はちゃんと見てくれてるのかな?」
そんな思いを抱きながら、担任と顔を合わせる保護者も少なくありません。
小学校新1年生の保護者なら、なおさらです。

そういえば前に、「緊張して昨夜眠れませんでした」っていう保護者の方がいたよ…
そこでこの記事では、筆者が教育委員会の相談員として保護者さんから”担任の先生との関係”について、良いこともそうでないこともたくさんお聞きしてきた内容を踏まえ、
「保護者との初回の面談」で信頼関係をうまく築くための準備や進め方、心がけるべきポイントをわかりやすくお伝えします。
この記事を通して、”面談で出だしからやらかすことのないように”…そんなヒントをお届けできたらと思います。
初回面談の準備段階で押さえておくべきポイント
「面談で何を話すか」はもちろん大事ですが、それと同じくらい重要なのが事前準備です。
限られた時間の中で信頼関係を築くためには、準備段階でどれだけ「安心の土台」を整えられるかがカギを握ります。
ここでは、面談前に押さえておきたい3つのポイントをご紹介します。
面談の目的とゴールを明確にする
「とりあえず情報交換を…」という曖昧なスタンスで面談に臨むと、雑談で終わってしまいがち。
初回の面談の目的とゴールは、次のように明確にしておくことが大切です。
| 面談の目的 | 保護者と信頼関係を築くための「初対面の場」 |
| 面談のゴール | 保護者が「この先生に話して大丈夫」と感じられる状態にすること |
「支援方針を決める」や「評価する」ことを目的の中心にしてはいけません。
あくまで信頼の土台を築くこと。
その意識で臨むことで、自然と言葉選びや対応も変わってきます。

つい、「支援の方向性を決めて、保護者さんと確認し合わなきゃ。」って前のめりになっちゃうんだよね。

方向性はまだ後からで十分。初回は、”お互いに顔見知りになる”、くらいに捉えるのがちょうどいいかも知れませんね。
面談シートや配布資料の工夫
初回面談では、「何を話したか」が保護者の記憶に残りづらいこともあります。
そこで有効なのが、簡潔で見やすい面談シートや資料の準備です。
おすすめは、以下のような構成の「1枚シート」。
- お子さんの好きなこと・得意なこと
- 学校生活での様子(写真やイラストがあると◎)
- 学校として大切にしている支援の姿勢
- 担任の自己紹介(教育観や関わり方のスタンス)
たとえば、「朝のルーティン」や「困ったときの対応例」などを写真付きで載せるだけで、イメージが湧きやすく、保護者の安心感がぐっと高まります。
お子さんについての項目以外は使い回せますし、あまり手間がかからないわりに「丁寧感」がめちゃくちゃ出るので、ベースになるものを1つ作っておくと便利です。

去年は学級の運営方針のプリントと支援計画を渡したよ。

継続で慣れている保護者さんならそれでもいいかもですけど、初めての保護者さんは、それだと「説明された」感はあっても、「寄り添ってもらえた」という印象が残らないかも知れませんね。
保護者の事前情報の整理と把握
事前に保護者から得られる情報は、面談の安心感につながる重要な材料です。
たとえば以下のような情報を、連絡帳や合理的配慮の申請などを通して個別に把握しておくとよいでしょう。
- 家庭での呼び方(例:本人が“たっくん”と呼ばれているなど)
- 保護者が気にしていること(例:「音に敏感で…」など)
- 通院や診断の有無(必要に応じて)
前年度に”個別の教育支援計画”や”個別の指導計画”を作成しているお子さんについては、そこに書かれている「保護者の希望欄」もチェックしてみましょう。
1つでいいので、そのことについて、最近のお子さんの様子やそこから自分なりに解釈したことをメモにしておくといいですよ。
保護者の立場としては、「前もって子どものことを知ろうとしてくれる先生」に出会うと、それだけで信頼感がアップします。

「お兄ちゃんのクラブの先生ですよね」と言ってくれた保護者さんがいて、知っててくれたんだ!って嬉しかったなぁ。

同じことを、保護者側も感じてますよ。“うちの子のこと、ちゃんと気にしてくれてる”って。そういう所から、「温度感」が伝わるものです。
準備は、信頼づくりの第一歩
面談は始まる前から始まっています。
話す内容だけでなく、「どう迎えるか」「どんな姿勢で臨むか」——その準備が、保護者との関係の質を大きく左右します。
保護者の信頼を得る「面談の進め方」
初回面談で「この先生になら安心して任せられる」と思ってもらえるかどうかは、話し方・態度・スタンスの3つにかかっています。
ここでは、面談を効果的に進めながら保護者との信頼関係を築くためのコツをご紹介します。
第一印象で安心感を与える態度・言葉
「第一印象が9割」と言われるほど、最初の数分はとても重要です。
笑顔+落ち着いた声のトーン
挨拶にプラス一言:「お子さんの様子をお聞きするのを楽しみにしていました」
視線の位置やうなずきなどの非言語コミュニケーション
たとえば、「よろしくお願いします」の前に「今日はお忙しい中ありがとうございます」と伝えるだけでも、場の空気がふっとやわらぎます。

”今の時間は、〇〇さんはどうされてるんですか”と質問すると、学童・習い事・お留守番・おじいちゃんおばあちゃんが面倒を見てくれるなどの答えが返ってきて、「えらいですね」的な会話に自然とつながり、家庭環境のリサーチもできるのでおすすめです。

何時ごろまで大丈夫かを聞くのも、配慮感があってウケがいいよ。
話し方の工夫(専門用語の避け方・伝え方)
特別支援に関わると、つい専門用語が口をついて出てしまいますが——
✕「視覚支援を活用しています」
〇「見てわかるように、絵カードや写真で流れを伝えています」
このように具体的な言い換えを心がけましょう。
また、「〇〇という方法がありまして」と前置きしたうえで専門用語を使えば、理解のハードルを下げられます。
共感・傾聴を示すリアクションのコツ
保護者の言葉に、適切にうなずく・繰り返す・共感する
この3つをバランスよく使えると、面談の安心感がアップします。
「朝、なかなか準備が進まないんです」
→「朝ってバタバタしますよね…。うちもです」
「病院で“ADHD傾向がある”と言われて…」
→「そうでしたか…。それを聞いたとき、どんな風に思われたんですか?」
ポイントは、“アドバイスより共感が先”という姿勢です。

“気にしすぎないでください”って言ったら、なんか微妙な空気になっちゃって…。安心してもらおうと思って言ったんだけどなぁ。

先に、たとえば「それは不安ですよね」とか言えたら良かったかもね。
「伝える」より「一緒に考える」スタンスが信頼を生む
初回面談での大きな落とし穴が、“先生からのお話タイム”で終わってしまうことです。
一方的に説明されるより、一緒にお子さんのことを考えていると感じられる関わり方が、信頼につながります。
「〇〇の場面でこういった様子が見られます。ご家庭ではどうでしょう?」
「こちらではこんな対応を試してみようと思いますが、どう感じられますか?」
このように双方向のやり取りを意識することで、「理解してくれる先生」という印象が残りやすくなります。
まとめ:技術より“心の姿勢”が伝わるかがカギ
初回面談の進め方においては、話し方や表現方法の工夫も大切ですが、もっとも伝わるのは“どんな気持ちで向き合っているか”です。
一番伝えたいのは、「あなたのお子さんを大事に思っています」というメッセージ。
それが伝わったときに、保護者さんの緊張が解けると思います。
保護者の不安に寄り添う具体的な対応例
よくある保護者の不安とその背景
特別支援にかかわる面談では、「お子さんの今の様子」や「将来への不安」が主なテーマになりがちです。しかしその背後には、もっと根深い感情が潜んでいることも多いのです。
たとえば、以下のような「よくある保護者の不安」があります:
不安の言葉①

ちゃんと授業についていけてますか?
背景にある本音は…

1人だけ取り残されたらどうしよう?
不安の言葉②

このままでは将来が心配で…。
背景にある本音は…

自分の育て方が悪かったのでは?
不安の言葉③

先生もお忙しいとは思うんですけど…。
背景にある本音は…

うちの子放置されてる?この先生、いっぱいいっぱいなのかな?
「学校での様子は問題ないですよ」とさらっと言われると、逆に「ちゃんと見てもらえているのかな?」と不安になってしまうことがよくあります。
そういった不安の多くは、“困っているのは自分たちだけかもしれない”という孤立感から来ている場合があるので、
まずは保護者の気持ちや考えをじっくり話してもらう(抱えている不安を吐き出してもらう)ことが大切です。

その場ですぐに保護者の不安を解決しなくちゃと思う必要はありません。「そうでしたか。特に気になるという印象はありませんが、しばらく学校でも気をつけて見ていくようにします。」でOKですよ。
上手な先生は、
学校での様子や、発達段階に照らし合わせた時の妥当性、生活年齢で見た場合の課題点などに触れながら、
「だから問題ない」のか「問題はないわけではないが、他の課題点のほうが優先度が高い」のかを、説明したりしているようです。

先生の考えがわかると、保護者の方も安心するんだって。

そうです。不安は”わからないこと”に対して生まれる感情なんです。
不安に対する共感的な言葉かけの実例
保護者との面談で信頼を得る鍵は、「アドバイス」より「共感的な言葉かけ」です。
たとえば、以下のようなフレーズは、保護者の心をやわらげます。
「おうちでのご様子をお聞きして、“ああ、やっぱりがんばっていらっしゃるんだな”と感じました」
「“うちの子だけが…”って思ってしまうお気持ち、よくわかります」
「“本当にこれでいいのか”って、きっと何度も自問自答されてきましたよね」
こうした言葉には、「あなたの感じ方はおかしくないですよ」というメッセージが込められています。

共感って、むずかしくないですか?「わかります」って言っても嘘くさく聞こえないかなって…

“わかろうとしてます”って態度のほうが大事。“同じじゃないけど、耳を傾けてます”っていう誠意が伝わるだけで、空気は変わるよ。
話しづらい話題(診断・行動面など)への配慮
診断名や医療的な話題、行動面の課題点など、センシティブな話題を取り上げるときは、「配慮のある前置き」と「柔らかい言い換え」が鍵です。
たとえば…
「診断は出ていますか?」
→ ◎「医療機関などで何かご相談されたことはありますか?」
「こだわりが強くて…」
→ ◎「“自分のやり方”がしっかりあるお子さんですね」
「問題行動」
→ ◎「どうしても気になる行動が時折見られるので…」
話しにくい話題は、“確認”より“共有”の姿勢で伝えると、保護者の受け止め方も柔らかくなります。
信頼関係を深めるための「面談後」のひと工夫
「面談が無事に終わった…と思ったのに、そのあと保護者との関係がぎくしゃくしてしまった」
そんな経験、ありませんか?
実は、面談そのものよりも「面談後のフォロー」で信頼関係が深まるかどうかが決まることも少なくありません。
面談で生まれた信頼の芽をしっかり育てていくための「ひと工夫」をご紹介します。
面談記録の共有・確認の仕方
面談後、「先生が何をどう受け取ったのか」が保護者に見えないと、不安を残してしまうことも。
そこでおすすめなのが、簡単な記録メモの共有です。
たとえば以下のような文面を保護者にお渡しすると、安心感がグッと高まります。
《記録共有メモ例》
【お話しいただいたこと】
・ご家庭での困りごと(朝の支度、兄弟関係など)
・今後の希望(自分でできることを少しずつ増やしたい)
【学校としてできる対応】
・朝の支度について、始業前の声かけ
・給食後の視覚スケジュールを導入

あとから“言った言わない”にならないから、いいね!でもこれって、いちいち書くの大変じゃないですか?

簡単なテンプレを作って、部分的に書き換えるだけで大丈夫。“気にかけてますよ”という意図が伝わることが大事。個別の教育支援計画・指導計画に追記していくという手もあります。
共有の際は“確認”を意識しましょう。
「内容に誤解がないか、よろしければご確認ください」など一言添えると、信頼度がさらにアップします。
面談後のフォローコミュニケーションのすすめ

面談で話したこと、どうなったかな?
保護者はその後の様子が気になっています。
フォローの連絡は、特別な出来事がなくてもOK。むしろ“変化がない”ことも大事な情報です。
「先日お話しした声かけ、今週も継続しています」
「最近は落ち着いて過ごせていて、〇〇さんらしさが出ています」
「給食の場面で笑顔が見られましたよ」
“状況報告+安心材料+子どもの良さ”のセットで伝えると、保護者の心にしみこみやすくなります。

“報告がない=放置されてる?”って思われることがあります。やってみたけど上手くいかないなら「また違う方法やタイミングを工夫してみます」でいいんです。繰り返しになりますが、”わからない・情報がない”ということが保護者の不安を生み出すのです。

“子どもの変化を捉えようとしてくれてる”って伝わるだけで、安心してもらえる気がするね!
小さな連絡の積み重ねが信頼につながる
面談後の信頼関係は、「豪華な対応」ではなく、“さりげない連絡”の積み重ねで育ちます。
たとえば…
連絡帳のすみに「今日は〇〇の活動でニコニコしていました😊」
登校時に「今朝はランドセルがまっすぐでしたね〜」
作品展で「この配色、すごく独特で素敵です」と声をかける
こうした「ちょこちょこ関わり」が“この先生はちゃんと見てくれてる”という安心につながるのです。
保護者面談を「一度きりのイベント」にせず、日常の中に“つづき”をちょこちょこ挟む感覚でいると、関係が自然に深まっていきます。
まとめ:初回面談を通じて「保護者の教育パートナー」になるために
初回の保護者面談は、子どもをめぐる情報交換の場であると同時に、教員と保護者が「子育てのチーム」になれるかどうかの第一歩でもあります。
いくら専門的な知識や配慮があっても、保護者が「この先生とは本音で話せないかも…」と感じてしまえば、支援の質は発揮されません。
逆に、多少不器用なやり取りでも、「わが子を一緒に見てくれる先生がいる」と思ってもらえれば、それだけで信頼関係はスタートします。

これまでたくさんの保護者さんと接してきましたが、若手の先生や支援学級が初めての先生だから信頼できない、といったようなことはありません。
面談に臨む際、重要なのは「正しい情報を伝えること」だけではありません。
それ以上に問われるのは、“どんな姿勢で保護者と向き合うか”という点です。
「うまく話さなきゃ」と気負うより、“私はあなたのお子さんの成長を応援しています”というスタンスを全身で伝えることが、何よりの安心材料になるのです。
もちろん、信頼関係は一回の面談だけでは完成しません。
日々の小さな積み重ね――連絡帳の一言、下校時の挨拶、作品へのコメント。
そういった”ふとしたこと”の一つ一つが、「この先生はちゃんと見てくれてる」という信頼の土台になっていきます。
でも、その“最初の一歩”があってこそ、後のやり取りもスムーズになります。
だからこそ、初回面談では「つながりのきっかけ」を意識してみてください。
この3つを押さえるだけでも、保護者との関係性は格段に良くなります。
面談は、教員にとっても「出会い直し」のチャンス。 子どもをまんなかに置いて、保護者と“味方どうし”になれるよう、小さな対話を大切にしていきましょう。