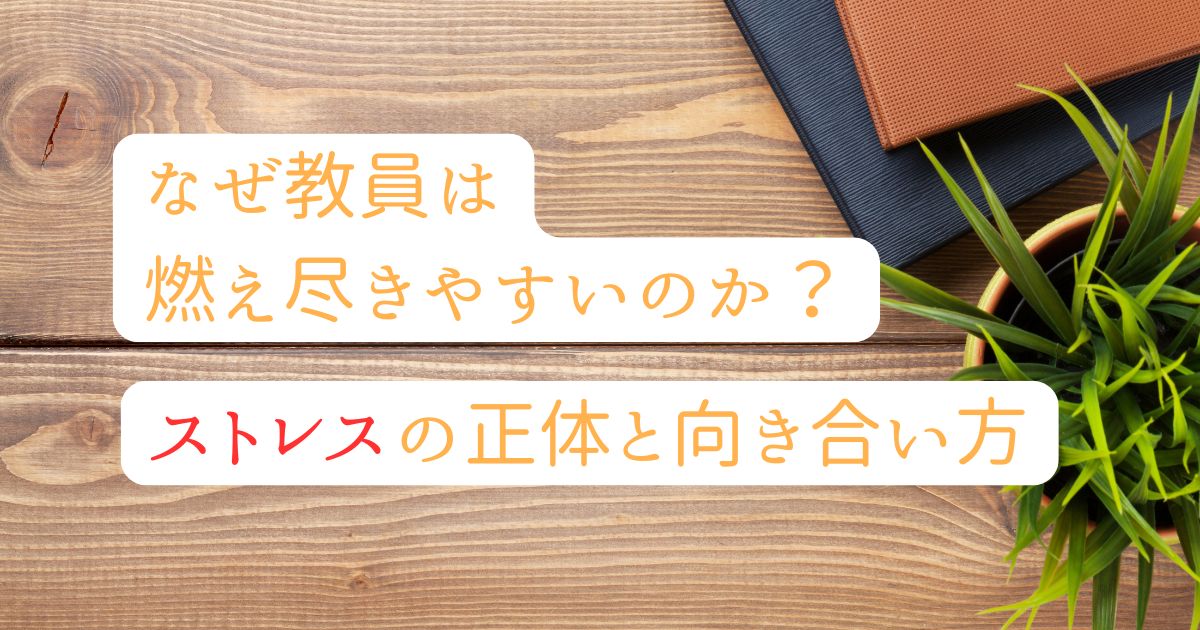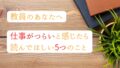こんにちは、公認心理師&セラピストのあべ子です^^
教育ニーズの多様化や業務の増加など、教員の負担は年々増大していると言われるようになりました。
授業準備や生徒指導に加え、保護者対応や事務作業など業務は多岐にわたり、「気付いたら今日はまだトイレに行ってなかった!」、なんて日もあるのではないでしょうか。
このような状況の中で、先生自身がこころと体の健康を維持することは、元気に仕事を続けていく上では極めて重要です。
そこで今回は、教師の燃え尽き症候群について一緒に考えてみたいと思います。
これを読めば、教師が燃え尽き症候群に陥るストレス要因とその対処法がわかるようになると思います。
教員特有のストレス要因

多岐にわたる業務と時間的制約
教員の仕事は、授業だけでなく様々な業務があり、いつも忙しさに追われていることが大きなストレス要因となっています。
授業の準備、生徒指導、保護者対応、校務分掌など、様々な役割をこなす必要があります。
これらの業務は時間外にやらざるをえないことも多く、ワークライフバランスの崩壊を引き起こします。
例えば、私の父は中学校教師でしたが、平日の夜遅くまで仕事をし、休日も部活動の指導や試合で朝早くから出かけるといった状況が珍しくありませんでした。

自分の時間が持てず、心身ともに疲弊してしまう先生が出てきても不思議じゃないね。
人間関係の複雑さ
学校の先生は、子どもたち、保護者、同僚、管理職など、多様な人々と関わる職業であり、これらの人間関係の複雑さがストレスの要因になる場合があります。
特に、困難を抱える子どもたちへの対応や、要求の厳しい保護者とのコミュニケーションは大きな精神的負担となります。
例えば、いじめ問題への対応や、学校の方針に不満を持つ保護者との話し合いなどは、高度なコミュニケーション能力と精神的なタフさを要します。
これらの人間関係のストレスは、教員の心の健康に大きな影響を与え、燃え尽きのリスクを高めるのです。

特に、若手の先生たちは、保護者対応がこじれたときの悩みが深刻になりやすい印象です。
社会からの高い期待と責任
教育には、社会から高い期待が寄せられています。
これは、教育が社会の基盤を形成する重要な役割を担っているからです。
こういった期待と責任が重圧となり、先生たちのストレスの要因となることがあります。
例えば、学力向上はもちろんのこと、いじめ・不登校対応、交通ルール、騒音、地域との関係…学校に対する要求は年々多様化・複雑化しています。

コロナの時も大変だったなー。
正当な指摘や、学校がある程度は責任を持つべき事柄であれば良いのですが、過度な要求やほとんど言いがかりのようなクレームなども、実際にはありますよね。
このような状況下で、自分の頑張りが十分な結果に結びつかないと感じると、自己効力感の低下や無力感につながり、燃え尽きの原因となるのです。
燃え尽き症候群の兆候と原因
燃え尽き症候群の定義
燃え尽き症候群は、以下の3つの症状から定義されます。
- 情緒的消耗感
- 仕事を通じて、情緒的に力を出し尽くし、消耗してしまった状態。
- 脱人格化
- クライアントに対する無情で、非人間的な対応。
- 個人的達成感の低下
- ヒューマンサービスの職務に関わる有能感、達成感。(消耗及び喪失)
これは、単純に仕事に疲れたということではありません。
あらゆることに心を配りながら、パフォーマンスやモチベーションの維持向上のために工夫をし、熱心に仕事に取組み、精一杯努力を重ねてきた結果、心のエネルギーがすっかり枯渇してしまった状態です。
周囲の人を思いやる余裕もなくなり、仕事の質が低下し、達成感や評価も得にくくなって、さらに意欲ややりがいが感じられなくなるという悪循環に陥ります。
燃え尽き症候群の兆候
燃え尽き症候群の主な兆候は、極度の疲労感と無気力です。
常に全力で仕事に取り組むタイプの先生が少なくなく、心身ともに疲れ果ててしまう傾向があります。
例えば、休日も仕事のことが頭から離れず、十分な休養が取れないという状況がよく見られます。
朝起きるのがしんどくなったり、仕事に行きたくなくなる人も出てきます。
この状態が続くと、やがて「どうでもいいや」「何もしたくない」という無気力感に襲われ、仕事への意欲を失ってしまいます。

休みの日に無人の学校に隕石が落ちてくれないかな…って思ったことあるよ。

それは相当きてますね💦
その他にも、お酒の量が増える、人との関わりが億劫になる、焦りはあるのに仕事が進まない、といったことも挙げられます。
燃え尽き症候群の原因
環境要因
燃え尽き症候群の原因として、環境要因や人間関係の影響が大きいことが分かっています。
教員の場合、長時間労働であることに加え、職員室での人間関係や管理職との関係に問題が生じると、燃え尽き症候群やうつ病のリスクが高まります。
例えば、同僚との意見の相違や、管理職からの期待や要求に対する十分なサポートが得られないなどがストレスの原因になっていきます。
良好な職場環境の維持が、燃え尽き症候群の予防に重要な役割を果たします。

環境はすぐに変えられないよ。どうしたらいいの?

無理をして一人で頑張ろうとせず、自分自身のケアを優先してください。仕事のオンオフを切り替えたり、「自分にできるのはここまで」と線引きしたりしても、罰は当たりません。
個人要因
燃え尽き症候群になりやすい性格特性というのもあります。
- 真面目で完璧主義
- 自分が頑張って何とかしようとする
- 期待以上の成果を出さねばと思う
- 他者への共感性が高く、感情移入しやすい
などがあります。

めっちゃええやつやん

自分に自己犠牲の傾向があるなぁと思ったら、ちょっと気を付けたほうがいいかも知れませんね。
ストレスと向き合うための自己認識の重要性
私たちがストレスと向き合うためには、まず自分自身の状態を正確に認識することが不可欠です。
自己認識とは、自分がどのような状況でストレスを感じやすいのか、どのような感情や反応が生じているのかを理解することです。
「授業準備が間に合わないと焦りやすい」「保護者対応で不安を感じる」など、自分のパターンを把握することで、適切な対策が取りやすくなります。

たとえば「授業準備が間に合わない」というのも、完璧主義だからなのか、スケジュール管理が下手だからなのか等、掘り下げていくとより有効な手立てが見えてきます。
また、自分にできること、できないこと、得意、苦手などの自己理解も大切です。
そして、できないことや無理なことは、一人で抱えていても良い結果を生み出しませんから、周りの人に助けを求め、知恵を借りましょう。
そして、自分の体がどんな状態になったら”そろそろ休息したほうがいいか”を知っておくことも非常に重要です。
このように自己認識は、ストレス軽減の第一歩であり、健康的に仕事を続けていくための土台でもあるのです。

だけど、己の無能さを認めるのはツライなー。

「現状、自分的によくやってるよね。」っていうスタンスが基本で、より良くするために、という風に考えるといいですよ。
日常的なストレス解消法

「小さなリフレッシュ」を習慣化する
日々の中で短時間でもリフレッシュできる習慣を取り入れることが、ストレス軽減に効果的です。
教員は多忙なスケジュールの中で、まとまった休息を取るのが難しいことが多いですが、短時間のリフレッシュでも心身を回復させる効果があります。
特に、意識的に「今この瞬間」に集中することで、思考の過負荷を軽減できます。
例えば、授業の合間に深呼吸を数回行う、昼休みに窓際で景色を眺める、好きな音楽を5分だけ聴くなど、小さな行動がストレス軽減に繋がります。
こうした「小さなリフレッシュ」を日常的に取り入れることで、忙しさの中にも心の余裕を作り出すことができます。
運動と睡眠で心身を整える
適度な運動と十分な睡眠は、ストレス解消に欠かせない基本的な要素です。
運動はストレスホルモンであるコルチゾールを減少させ、脳内の幸福感を高める物質(エンドルフィン)を分泌します。
睡眠不足はストレス耐性を低下させるため、質の良い睡眠を確保することも重要です。
通勤時に一駅分歩く、寝る前に軽いストレッチを行うといった簡単な運動から始めてみましょう。
また、寝る前1時間はスマホやパソコンの使用を控えることで、深い眠りにつきやすくなります。
運動と睡眠は教員としてのパフォーマンス向上にも繋がるため、意識して生活に取り入れることが大切です。

睡眠の問題は自律神経の乱れも関係しています。
仲間とつながり、「話す」ことで心を軽くする
信頼できる同僚や友人と話すことは、ストレス解消に非常に効果的です。
教員は孤立しやすい職業と言われますが、自分の悩みや感じている負担を共有することで気持ちが軽くなることがあります。
他者との対話は、自分一人では気づけない視点や解決策を得るきっかけにもなります。
「話す」ことで感情を整理し、人とのつながりから安心感を得られる効果が得られますから、一人で抱え込まず周囲とのコミュニケーションを大切にしましょう。
周りの人に知られたくない、心配をかけたくないという場合は、カウンセラーなど第三者を頼るのも一つの手です。

「わかってるけど、そんなことやっている余裕なんかない!」って思う人もいるんじゃない?

ここに挙げたことすらできないのは深刻ですよ。それぐらい追い詰められているんだ、ってまずは自覚したほうがいいですね。

とりあえずバナナを食べましょう。
バナナにはセロトニンと、その材料となるトリプトファン、セロトニン生成を助けるビタミンB6や、抗ストレスホルモンの生成に関わるビタミンCも含まれているため、エネルギー補給だけでなくリラックス効果も期待できます。セロトニンは夜になるとメラトニンを生成し、睡眠を促す働きもあります。
まとめ:教師という仕事を続けていくために
教師の仕事がつらい・しんどいと思っている先生も、もともとは夢や理想を持って教職についた人が多いはず。
それを一生の仕事として続けていくためには、自身のストレスと向き合い、マネジメントすることが不可欠です。
教員特有のストレス要因を理解し、燃え尽き症候群の兆候に早めに気づくことが重要です。
長期的に充実した教員生活を送るためにも、まずは自己のウェルビーイングを大切にするという視点を持ち、自己認識を深め、バナナを食べながらこまめなストレス解消を取り入れてもらえたらと思います。