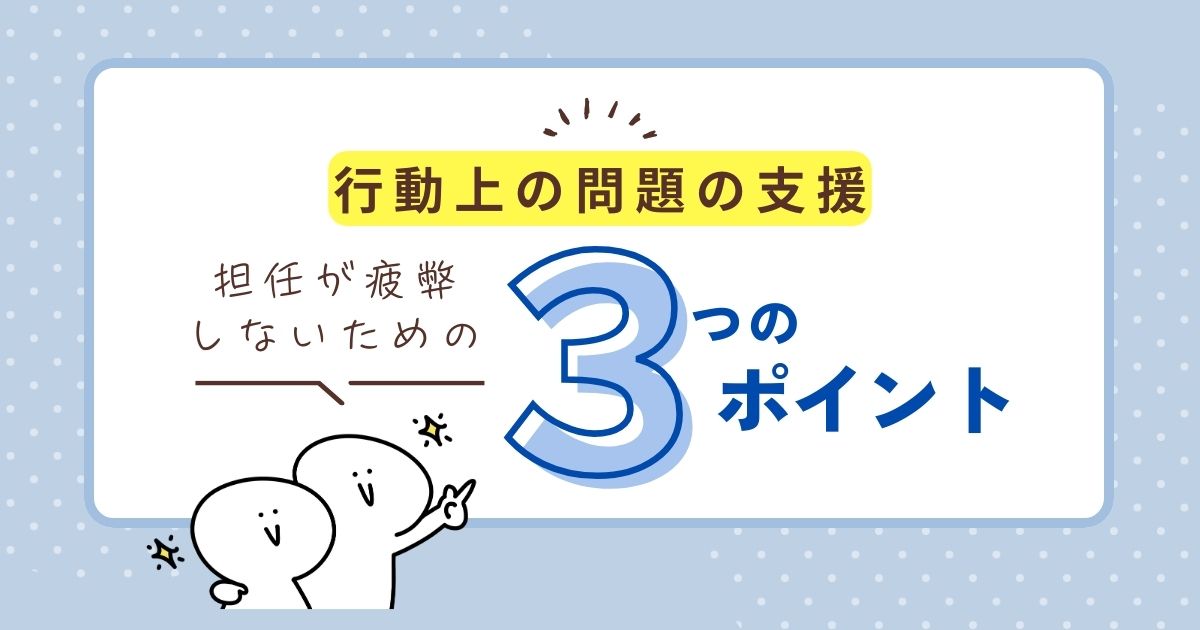こんにちは、公認心理師&特別支援教育士のあべ子です^^
こちらの記事で、暴言や他害といった行動面に課題のある児童への指導に悩まれている先生がいらっしゃったのですが、特に情緒学級では、行動面への対応が必要になることは少ないと思います。
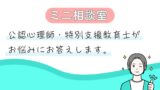
そこで今回は、その対応の仕方について基本的な考え方についてまとめました。
ポイントを簡単にまとめると、以下の3つになります。
ポイント1:行動の持つ意味や機能の理解
ポイント2:適切な行動の獲得支援
ポイント3:全人的理解
この記事を読んで、子どもの行動の捉え方がわかり、指導目標が立てやすくなったり、自分が何をすべきかの糸口が見つかるといいなという気持ちを込めて書きました。
ぜひ明日からの実践に活かしていっていただけたらと思います^^
行動の持つ意味や機能を理解する
指導するにあたっては、暴言や他害をするには”それなりの理由や背景”がその子にはあるんだということを、まず押さえなくてはなりません。
暴言や他害というのは、それをすること自体が目的なのではなく、その子にとって何かを手に入れたり、回避したり、あるいは表現するための”手段”だからです。
その「何か」が何なのかを、まず突き止めましょう。
たいていの場合、突き詰めると、何らかの不快な状況を解決したいというネガティブな理由が発端になっていることがよくあります。
例として、自分のイライラの持っていき場がなくて八つ当たりしている場合もあれば、そうすれば誰かが自分をかまってくれるという注意引きの場合もあるでしょう。
あるいは暴言・他害をすれば授業がストップし、やりたくない課題をやらずに済むという場合もあるかも知れません。
これらの行動を、「その不快な状況を解決するには、ご本人が現時点で持っている手段の中でそうするしかないからそうしているんだ」という風に捉えることで、
行動上の問題を、その子自身の問題ではなく、その子とその子を取り巻く環境との関係性の中で起きる問題、と言う風に改めて捉え直していきましょう。
このような、どんな背景やきっかけによって暴言や他害が発生し、その結果この子がどんなことを得ているのかを把握することを、「機能的アセスメント」と言います。

予防策も取れるようになるよ。

感覚処理の特性が背景にある場合は、環境調整の必要があるので、実態把握は丁寧に行ってください。
望ましい行動や表現を使えるように指導する
暴言や他害が持つ意味(機能)がわかれば、
ちなみに、巷であるあるなのが、「暴言を言わない」「他害をしない」といった表現。これはナンセンスです。
理由は簡単で、「〇〇するな」と言われても、子どもにしてみれば「じゃぁどうすりゃいいんだよ」というツッコミしか生まれないからです。

「廊下を走るな」と言われて匍匐前進した猛者がいたな。

「廊下は歩きましょう(歩きます)」が正解だねぇ。
そうではなく、問題となる行動以外の方法でそれを満たせるようにする、すなわち、暴言や他害をしなくても済むようにする、という方針が良いと思います。
そもそもの適応的な行動が身についていない「未学習」の場合は、SSTや機会利用型指導などを用いて行動形成していきましょう。
その他にも、先ほどの例で言うと、以下のような指導が考えられます。
大切にしたい心構え
理由は何であれ、暴言や他害は容認できることではありません。
体を張って止めないといけないし、言われた側・やられた側へのケアも当然しなくてはなりません。
だからこそ、その子が社会の一員として適応的な社会生活を送るために、そういったことをしなくても済む力を身につけさせるのが教育の役割でもあります。
ただ、大切な心構えとして、不適切な行動に対して指導するという視点だけではなく、その行動のベースとなっている「この子がどんな世界の中に生きているのかを理解する」という視点(全人的な理解)を忘れてはなりません。
その子がどんな制約の中で何を経験し、どんな感情を味わっているのか、本当は何を望んでいるのか、という視点で、今起きていることを眺めてみて下さい。
そうせざるを得ないというその子の事情・心情を汲むという視点があるのとないのとでは、その子への向き合い方と関わりの質が劇的に違ってくるはずです。
そのような眼差しを向けてくれる大人、心情を汲み取った関わりをしてくれる大人が、果たして今までその子の周りにいたでしょうか(多分いないのではないかと思います)。
そのような全人的な関わりをしてもらう経験が、その子だけでなく周りの子どもたちにとっても、今後の人生にどれほどの恩恵をもたらすかは、言うまでもありません。

余談ですが、暴言や他害が見られる場合、家庭環境のリサーチも頭の片隅に入れておきましょう。
まとめ
行動上の問題に対して、機能的アセスメントの結果にもとづいた支援アプローチが有効であると言われています。
- どんな時に
- どのような行動が見られたら
- どのように対応する
これを個別の指導計画の中に明記しておくことで、担任の先生だけでなく、交流級の先生、支援員、その他の先生など、児童に関わるすべての人で共通の対応が取れ、より効果的な支援ができるようになりますよ。

具体的にどうやったらいいか分からない場合は、実際のケースについて一緒に考えることもできますので、お問い合わせフォームからご連絡ください^^