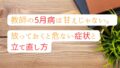「自分がわからない」とは?
「自分がわからない」と感じてしまうのは、あなたが他人を大切にしてきた証です。
「私はいったい、何者なんだろう?」
ふとした瞬間に、そんな感覚に襲われることはありませんか?
それは、あなたが長い間、他人の期待や価値観を優先し、「自分よりも他人を優先する」ことを無意識に選び取ってきた結果かもしれません。
心理カウンセリングの世界では、これを「他人軸」と言います。
子どもの頃から「こうするのが正しい」「人に合わせることが望ましい」といった価値観に囲まれて育つと、本来の自分の感覚や欲求よりも、周囲の評価や反応を優先するクセがついていくのです。
そのようにして生きてきた方が、「私はどうしたいのか?」という問いにうまく答えられなくなるのは、ごく自然なことです。
*
他人を優先するクセは、あなたが“優しさ”や“生き延びる術”として身につけたもの
「いつも自分よりも他人を優先してしまう」「つい遠慮してしまう」
そうした傾向は、決して“悪いこと”ではありません。
むしろそれは、あなたがまわりの人の気持ちに敏感で、他者との調和を大切にしてきた証。人間関係の中で円滑に生きるために、とても大事なスキルでもあります。
また、心理的に言えば、他人を優先することで安全を確保したり、自分の存在価値を感じたりする“適応的な戦略”であった可能性もあります。
特に、子ども時代に「いい子でいなければ愛されない」といった経験を持つ人は、自分よりも他人を優先することが生き延びるための知恵だったのです。
ただ、その“優しさ”がいつの間にか自分を見失う原因となってしまっているなら、少しずつ立ち止まって、自分の声に耳を傾けることも大切です。
“自分の声”を取り戻すリハビリ
では、自分とのつながりをもう一度取り戻すには、どうしたらよいのでしょうか。
まずおすすめしたいのは、日常のなかで小さな「私はどうしたい?」を拾い集めていくことです。
たとえばこんなふうに、自分の感覚に目を向けてみてください:
- 今、どんな飲み物が飲みたい?
- この瞬間、どんな音楽が心地よく感じる?
- 今夜のお風呂、どんな香りの入浴剤がいい?
こうした“なんでもない選択”の中にこそ、実はあなたの「本音」や「今の気分」が隠れています。
そして、そうした感覚を言葉にしたり、実際に行動に移してみることで、少しずつ自分の内側とつながるアンテナが整っていくのです。

リアルに想像してみると、自分の好みが少しずつ見えてきます
たとえば「水が飲みたい」と思った時も、それをもう少し細かく想像してみましょう。
- 水道水をコップに入れて飲むのがいい?
- 冷えたミネラルウォーターを一気飲みしたい?
- それとも、炭酸水をおしゃれなグラスに注いでゆっくり味わいたい?
こんなふうに、同じ「水を飲む」という行動でも、感じ方や好みは人それぞれです。
自分にぴったりくる選択を探る練習を重ねることで、「自分に合うもの」「自分らしい感覚」に気づく力が養われていきます。
「好き」さえもわからない時は
もし、「好きなもの」「これがいい」という感覚すら曖昧でよくわからない……というときは、無理にポジティブな感覚を探そうとしなくても大丈夫です。
その場合は、
「これは違うな」「これは今の気分じゃない」
という“NO”の感覚からスタートしてみてください。
たとえば、着る服を選ぶときに「これはなんかしっくりこない」「今日はこの色じゃない」と思えるなら、それも立派な“自己感覚”です。
それだけ、あなたの内側にまだ感覚が残っているということ。
ずっと抑え込んできた分、最初はうまく言語化できなくても当然です。
焦らず、ゆっくりと、自分との対話を始めてみてください。
あなたの中の「本当の声」は、ちゃんとそこにあります。

大切なのは、大きな変化ではなく、“小さな選択”の積み重ねです。
自分らしさを取り戻す第一歩は、日々の生活の中で簡単に始められますよ^^